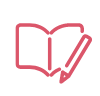ここから本文です
あしあと
定期の予防接種(乳幼児・児童生徒対象)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1086
お子さんを感染症から守るため、また、感染症の流行を防ぐために予防接種を受けましょう。
予防接種は、医療機関での個別接種でおこなっています。
予防接種の種類によって、おすすめする接種時期、無料で受けられる対象年齢が異なります。対象年齢を過ぎた場合や、項目にない予防接種を受けられた場合は、費用の全額を自己負担でお支払いいただく「任意接種」となりますのでご注意ください。
麻しんおよび風しんの定期予防接種の接種期間延長について
現在、一部地域においてMRワクチンの偏在等が生じていることから、令和6年度中に接種対象期間を迎えた方で、期間内に接種できなかった方の接種期間が延長になりました。
接種期間延長の対象者
第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた方
第2期:平成30年4月2日から平成31日4月1日までに生まれた方
接種期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
乳幼児・学齢期の定期予防接種の対象疾病
- ロタウイルス感染症
- 小児肺炎球菌感染症
- B型肝炎
- ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、ヒブ感染症
- 結核(BCG)
- 麻しん、風しん
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
接種方法
接種の流れ
- 対象年齢・回数・接種間隔等を保健だより等で確認してください。
- 個別接種実施医療機関へ直接電話などで予約してください。その際、予防接種の種類・受ける子どもの氏名・生年月日・住所・電話番号・予診票の有無を医院に伝えてください。
※体調のよい時を見はからって予約してください。 - 予約をしたら、指定の日時に接種を受けてください。
※急に受けられなくなったときは速やかに個別接種実施医療機関へ連絡ください。
※事前に、「予防接種と子どもの健康」(生後2か月の乳児訪問時に配布していますが、転入の場合や紛失された場合は、健康推進課または、個別予防接種実施医療機関に据え置きしています。)などを読んで、受ける予定の予防接種の必要性や副反応について理解をしてから受けてください。
持ち物
- 母子健康手帳
- 予診票(生後2か月の乳児訪問時に配布していますが、ご転入の場合や紛失された場合は、健康推進課または予防接種実施医療機関に据え置きしています。)
- 住所確認のできるもの(京都子育て支援医療費受給者証など)
接種場所
医療機関によって接種できる予防接種が違いますので、以下の添付ファイルを参照ください。
対象年齢・回数・接種間隔等
※麻しんおよび風しんの定期予防接種対象者で、令和6年度に接種できなかった方は接種期間が令和9年3月31日まで延長になりました。
異なる予防接種を受ける場合の接種間隔について
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。
詳しくは異なるワクチン間の接種間隔についてのページをご覧ください。
予防接種を受ける際の保護者の同伴や同意について
満15歳以下の方が予防接種を受ける場合
予防接種を受けるには、保護者の同意同伴が必要です。やむを得ない理由により保護者が同伴できない場合は、保護者の「委任状」に基づいて保護者以外の方の同伴が可能です。同伴者は、日頃からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。保護者とは、予防接種法第2条第7項の規定に基づき、「親権」を行う者または「後見人」をいいます。
ただし、13歳以上の方は、保護者の同意の署名があれば、保護者の同伴は不要です。その場合、事前に予診票の内容を読んでいただき、署名していただく必要がありますので、接種当日までに、健康推進課窓口または接種医療機関で予診票を受け取ってください。
※「委任状」は、生後2か月の乳児訪問時に配布していますが、転入の場合や紛失された場合は、健康推進課窓口でお渡しします。または、委任状(PDF形式、51.51KB)でダウンロードをしてご使用ください。
満16歳以上の方が予防接種を受ける場合
満16歳以上の方が次の予防接種を受ける場合は保護者の同意が不要です。
対象の予防接種:ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、日本脳炎(特例対象者)
京都府の広域予防接種事業について
京都府内の協力医療機関でも定期予防接種を受けることができます。かかりつけ医が協力医療機関であるかどうかの確認については、健康推進課へ問い合わせください。なお、医療機関によって接種できる予防接種が異なりますので、併せて問い合わせください。
予診票をお持ちでない場合は、健康推進課に問い合わせください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等の定期接種の機会の確保
定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情のため、定期予防接種を受けることができなかった方について、一定の期間、公費負担で接種することができるようになりました。
詳しくは長期療養等により定期予防接種が受けられなかった方についてのページをご覧ください。
予防接種に関する情報
厚生労働省ホームページ
相談先一覧
予防接種や感染症全般について
「感染症・予防接種相談窓口」では、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
- 【電話番号】0120-995-956
- 【受付時間】午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)
※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認められた方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
まずは、健康推進課まで問い合わせください。詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」別ウィンドウで開くでご確認ください。
お問い合わせ
木津川市健康福祉部健康推進課
電話: 0774-75-1219
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます