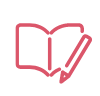ここから本文です
あしあと
健康づくりのための睡眠【実践編】
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1134
良質な睡眠のための環境づくり
ポイント
- 日中にできるだけ日光をあびると、体内時計が調整されて入眠しやすくなる
- 寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝ることが良い睡眠に繋がる
- 寝室は暑すぎず、寒すぎない温度で、就寝の約1時間から2時間前に入浴し身体を温めてから寝床に入ると入眠しやすくなる
- できるだけ静かな環境でリラックスできる寝衣・寝具で眠ることが良い睡眠に繋がる
光の環境づくり
起床後に朝日の強い光を浴びることで体内時計はリセットされ、睡眠覚醒リズムが整い、脳の覚醒度は上昇します。日中に光を多く浴びることで夜間のメラトニン(睡眠を促すホルモン)分泌量が増加し、体内時計が調整され、入眠が促進されます。
一般的には朝に光をあびると体内時計が前進(早寝・早起き化)し、夕方以降に光をあびると体内時計が後退(遅寝・遅起き化)します。朝目覚めたら部屋に朝日を取り入れ、日中はできるだけ日光を浴びるように心がけることで、就寝時の速やかな入眠が期待できます。
就寝約2時間前からメラトニンの分泌が始まります。それ以降に照明やスマートフォンの強い光を浴びると、催眠効果のあるメラトニンの分泌が抑制されることから、睡眠、覚醒リズムが遅れ、入眠が妨げられることが報告されています。
温度の環境づくり
人の深部体温(皮膚温ではなく、脳や臓器などの身体の内部の温度)は、およそ24時間周期で変動しており、日中の覚醒時に上昇し、夜間の睡眠時には低下します。就寝時に、手足の皮膚血流が増加することで体温が外部に放散され、深部体温が低下し始めると、入眠しやすい状態になります。
就寝の約1時間から2時間前の入浴は、手足の血管を拡張させることで熱放散を促進し、入眠を促す効果が期待できます。しかし、極端に湯温が高いと交感神経の活動が活発になり、かえって入眠を妨げる可能性もあります。
- 夏の室温
夏の室温上昇時に、睡眠時間が短縮し、睡眠効率が低下することが報告されているため、夏の室内はエアコンを用いて涼しく維持することが重要と考えられています。 - 冬の室温
十分に寝具を用いて、寝床内が暖かく維持できるようにしましょう。WHOの住環境ガイドラインは冬の室温を18度以上に維持することを推奨しています。特に冬の寒さは心疾患や脳卒中を予防する観点でも、夜中にトイレにいく場合や早朝起床時に急な寒さに曝されると、血圧が急激に上昇し、脳卒中や心筋梗塞の発症につながるおそれがあるため注意が必要です。
音の環境づくり
睡眠中の騒音は、覚醒頻度を増加させ、深い睡眠が減少することが報告されています。また睡眠中も、聴覚からの刺激は脳に伝達されて、自律神経系やホルモン分泌に影響する可能性があります。そのため、屋外の騒音が気になる場合には、十分な防音機能をもった窓や壁を設置して、騒音を遮蔽することも有効です。
運動、食事等の生活習慣と睡眠
ポイント
- 適切な運動習慣を身につけることは、良質な睡眠の確保に役立つ
- しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控えると、体内時計が調整され睡眠、覚醒リズムが整う
- 就寝前にリラックスし、無理に寝ようとするのは避け、眠気が訪れてから寝床に入ると入眠しやすくなる
- 規則正しい生活習慣により、日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつけることで睡眠の質が高まる
適度な運動習慣を身につける
睡眠は日中の身体活動等で消耗した体力等の回復の役割も担うことから、日中の身体活動量や強度が、眠りの必要量・質に影響します。
運動内容と時間
中強度から高強度の運動は睡眠の質や睡眠時間、睡眠効率を改善させると言われています。健康増進の観点からも、1日60分程度の身体活動を習慣化することが理想ですが、まとまって運動する時間がないからと諦めず、まずは1日60分未満でも定期的な運動習慣を確立し、少しずつ運動時間を増やしていきましょう。就寝前1時間以内の激しい運動は夜の眠りを妨げる可能性があるため、できる限り就寝の約2時間から4時間前までに終え、床に入るまでの間にリラックスする時間を設けると良いでしょう。
- 低強度の運動
家の中で歩く・ストレッチ・ヨガ・洗濯物の片付け・買い物・植物の水やりなど - 中強度の運動
息が弾み汗をかく程度の散歩・軽い筋力トレーニング・掃除機をかける・洗車をするなど - 高強度の運動
ジョギング・水泳・エアロビクス・サッカー・登山など
しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控える
朝食を欠食することで体内時計が後退(遅寝、遅起き化)することが報告されています。朝食を欠食すると、体内時計の後退に伴う寝付きの悪化を介し、睡眠不足を生じやすくなります。
また、就寝前の夜食や間食は、朝食の欠食と同様に体内時計を後退させ、翌朝の睡眠休養感や主観的睡眠の質の低下をさせます。さらに、夜食や間食の過剰摂取は、糖尿病や肥満をもたらし、閉塞性睡眠無呼吸の発症リスクも高めることが報告されています。
就寝前にリラックス
スムーズに入眠するためにはリラックスし、脳の興奮を鎮めることが大切です。そのためには、寝床につく前に少なくとも1時間は家事や仕事、勉強に追われずリラックスする時間を確保することが有効です。
また、睡眠時間や就床時刻に過剰にこだわり、眠気が訪れていないにもかかわらず無理に眠ろうとすると、寝付けないことを必要以上に悩んだり、日中の悩み事など寝床に持ち込み、余計に寝つけなくなります。なかなか眠れない時は、一旦寝床を離れ、寝床以外の静かで暗めの安心感が得られる場所で、眠気が訪れるまで安静状態で過ごし、眠気が訪れてから寝床に戻りましょう。
- オススメのリラクゼーション
瞑想法、静かに行うヨガ、腹式呼吸、音楽、アロマなど
睡眠と嗜好品
ポイント
- カフェインの摂取量は1日400mg(コーヒーを700cc程度)を超えると、眠りにくくなる可能性がある
- カフェインの夕方以降の摂取は、夜間の睡眠に影響しやすい
- 晩酌での深酒や、眠るためにお酒を飲むこと(寝酒)は、睡眠の質を悪化させる可能性がある
- 喫煙(紙巻たばこ、加熱式たばこ等のニコチンを含むもの)は、睡眠の質を悪化させる可能性がある
カフェイン
カフェインは覚醒作用を有するため、寝付きの悪化や中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる可能性があります。1日の摂取するカフェインが増えれば増えるほど深い眠りが減少し、中途覚醒が増え、睡眠効率が低下し、総睡眠時間が短縮することが報告されています。
アルコール
アルコールは一時的には寝付きを促進し、睡眠前半では深い睡眠を増加させます。しかし、睡眠後半の眠りの質は顕著に悪化し、飲酒量が増加するにつれて中途覚醒回数が増加することが報告されています。
ニコチン
たばこに含まれるニコチンは覚醒作用を有しており、睡眠前の喫煙は、入眠潜時の延長(寝付きの悪化)、中途覚醒の増加、睡眠効率の低下、深睡眠の現象をもたらします。また、ニコチンの血中半減期(血中濃度が半分になるまでの時間)は約2時間であるため、夕方の喫煙であっても、眠る前までその作用は残存することがあります。
その他のページ
次のページも併せてお読みください。
外部リンク
お問い合わせ
木津川市健康福祉部健康推進課
電話: 0774-75-1219
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます