学研都市線 鴻池新田駅
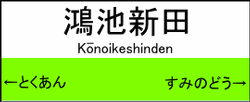
| 開設:明治45年4月21日 1日平均乗降客数:23.8千人(令和4年度) |
鴻池新田会所/東大阪市 |
|
 |
中世から近世にかけての河内の中央部には、「深野池」「新開池」の2つの大きな池があり、大和川が注いでいました。大和川はたびたび氾濫をおこし、人々を苦しめてきました。その被害を未然に防ごうと河内郡今米村の庄屋であった中甚兵衛は幕府に願い出て、宝永元(1704)年に大和川の付替え工事を完成させました。
この付替え工事によってそれまでの川床や池床が干拓され、新田として利用できるようになり、大阪の豪商であった鴻池家が巨額の経費をかけて新田の開発にあたりました。宝永4(1707)年に119haの新しい新田が開発され鴻池新田の名称が与えられました。新田を監督管理するために設けられたのがこの会所です。 昭和51年には国の史跡として、昭和55年には本屋等5棟が国の重要文化財の指定を受けています。 |
|
|
交通:鴻池新田駅下車すぐ
|
勝福寺(羅漢寺)と諸福菅原神社/大東市 |
|
  |
勝福寺は、十一面千手観音菩薩を本尊とする寺で、慶長元(1596)年に創建。多くの羅漢像が並べられていることから羅漢寺とも呼ばれています。本堂には座像が135体、立像が16体安置されています。
菅原神社は寛永20(1643)年に勧請されたもの。本殿は江戸初期の権現造りですが、桃山建築の雰囲気を残すもの。保存もよく華麗な色彩がうかがわれます。 |
|
|
交通:鴻池新田駅から北へ寝屋川を渡り古堤街道沿いに東へ。約18分
|
| 徳庵駅へ | 住道駅へ |
登録日: 2019年7月5日 /
更新日: 2022年9月30日




